母子ともに命がけで臨む出産。
がんばって生まれてきてくれたあかちゃんですが、産後すぐに治療や検査が必要になる場合もあります。
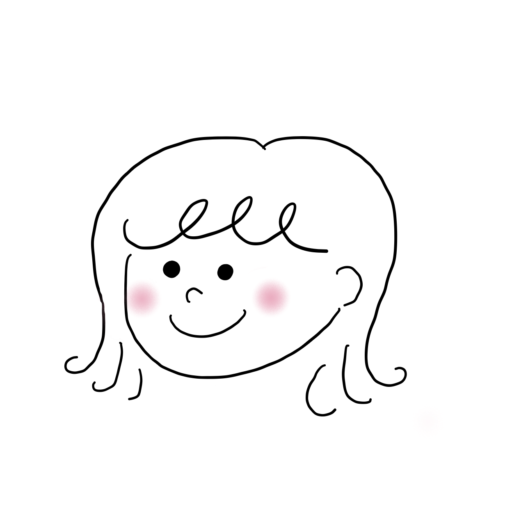 Utako
Utako我が家の息子は出産翌日にNICUに入院しました。
まだ健康保険証の発行どころか、出生届も提出していないままの入院…
お父さんやお母さんは、あかちゃんのことが心配で気持ちでいっぱいの中、医療費や行政手続きなどのことも考えなくてはならず、少々混乱することも。
また、新生児の入退院については、健康保険証の申請・発行が退院時の医療費の支払いに間に合わないなんてこともよくあります。
今回は、生まれてすぐに新生児が入院となってしまった時に必要最低限な申請手続きと、利用できる医療費の助成制度についてまとめてみました。
必要としている方へ届けば幸いです。
この記事では、我が家の息子が生後1日目に「新生児無呼吸発作」でNICUのある病院へ入院した際の手続きや利用できる公的制度、かかった費用などをシェアしています。
申請すべき公的な医療費助成制度


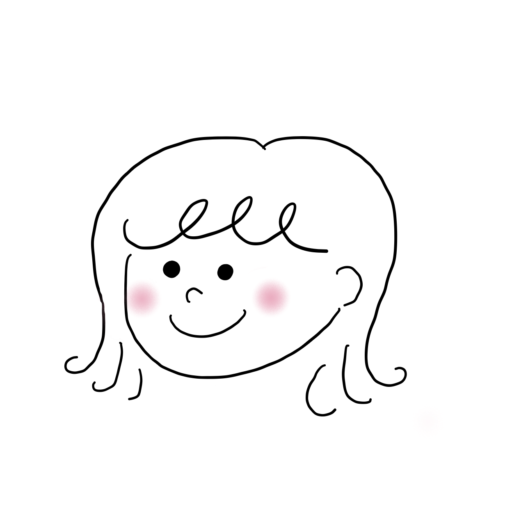
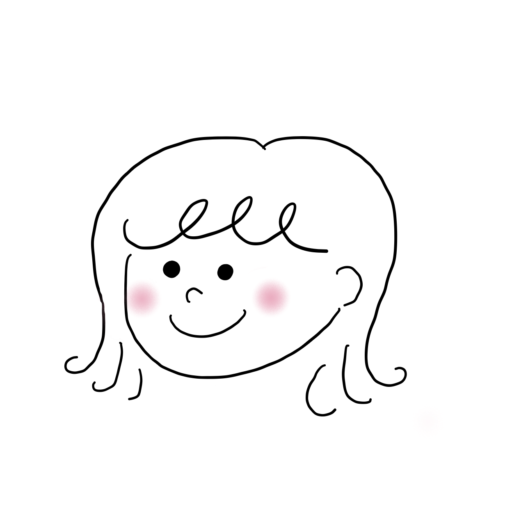
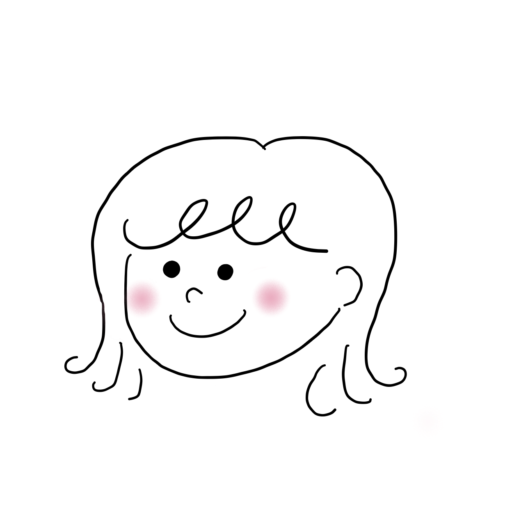
子どものことが心配でしょうがないけど、NICUの治療費は高額!費用のことも気になりました。
あかちゃんの治療や検査にかかる医療費に対して、利用できる公的な助成制度は主に「子ども医療費助成」と「高額医療費制度」の2つです。
万が一、産後あかちゃんに治療が必要となった場合は、できるだけ早くこちらの2つの制度の利用申請をしておきましょう。
子ども医療費助成(※自治体によって名称は異なる)
「子ども医療費助成」は、自治体によって制度の名称が異なりますが、あかちゃんの治療や検査、入院にかかった費用を自治体が負担してくれる制度です。
助成内容は自治体によって異なりますが、医療費無料、入院の場合は一日数百円で済むなど、負担がかなり軽減される内容となっています。
※助成対象となる費用は、保険が適用される医療費のみとなります。
健康保険証ができたらすぐに申請
申請には、「健康保険証」が必要です!
健康保険組合や国民健康保険の場合は自治体窓口で申請をしますが、「保険証」の作成は時間がかかる場合もあるため、出生届を提出したら、早めに保険証の申請をしておくことをおすすめします。
申請窓口
申請先は、各自治体の子育て支援の担当課が窓口となります。
持ち物は、「健康保険証」や「普通預金の通帳(償還払いの場合など返金に利用)」など。各自治体のHPをよく確認してから申請に行きましょう。
申請をすると「医療証」がもらえ、それを各医療機関の窓口で提示することで、「子ども医療費助成」を受けることができます。大体即日で出してもらえます。
他市・他県の医療機関を利用すると使えない?
「子ども医療費助成」を適用できる「医療証」は、他市・他県の医療機関では使えないことが多いです。
「医療証」が使えない医療機関を利用する場合は、一旦自己負担で医療費を支払い、後日お住まいの自治体窓口に申請することで、自己負担限度額以外の額を返金してもらうことができます。
医療費の支払いまでに、「子ども医療費助成」の申請が間に合わなかった場合
医療機関で医療費を支払う時点で、制度の申請ができていない場合も、一度窓口で全額支払い、後日お住まいの自治体で申請することで、償還払いを受けることができます。
我が家の場合は、里帰り出産だったので、他県の総合病院に入院しました。
一度自己負担し、居住する自治体に戻ってから申請し、償還払いで助成適用分を返金してもらいました。
高額医療費制度
「高額医療費制度」は、医療費が高額になってしまったときに、自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。
※自己負担限度額は、年齢や所得などによって異なります。
医療費が高額になりそうなとき、事前に「限度額適用認定証」の申請しておくと、1か月間に利用した1医療機関ごとの窓口での医療費の支払いが自己負担限度額分のみとなり、窓口で高額の支払いをせずに済みます。
医療機関の窓口で医療費を支払う時点で、「限度額適用認定証」を申請していない場合は、一度全ての医療費を支払った後に高額医療費制度の申請をして、返金してもらうことになります。
申請窓口
親が会社員の場合は、職場の福利厚生関係の担当部署に申請をします。
個人事業主の場合は、各自治体の国民健康保険の担当課に申請します。
他県の医療機関でも適用される?
子ども医療費助成と同じく、他県の医療機関では、限度額適用認定証を使うことができないため、一度全額自己負担し、後日健康保険組合に申請し、償還払いを受ける必要があります。
「こども医療費助成」と「高額医療費制度」の併用はできる?
併用はできません。
基本的に「こども医療費助成」は、「高額医療費」が適用される金額を差し引いた後に適用されます。
我が家の場合は、息子の退院時に、「健康保険証」だけは間に合ったので、自己負担3割分の医療費約22万円を支払い、居住する自治体に戻って申請し、「こども医療費助成」が適用される分を返金してもらいました。
先に「こども医療費助成」の申請をした際に、自治体窓口で「高額医療費制度」は利用できるのか尋ねると、「健康保険組合に問い合わせてみてください」と言われたので、夫の職場で聞いてもらったところ、「高額医療費制度」が適用となるものはありませんでした。
医療費約22万円のうち、17万円が「子ども医療費助成」の対象となり、返金されました。残りの分は、保険診療外の費用であったことや、「高額」と言えない金額だったため、「高額医療費制度」の対象にはならなかったようです。
産後すぐ・最短で公的続きを済ませる手順


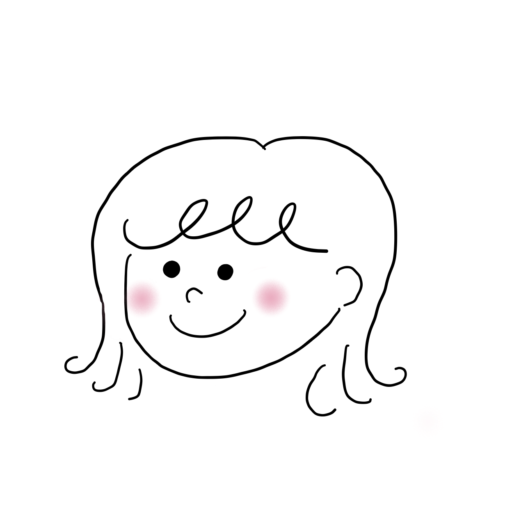
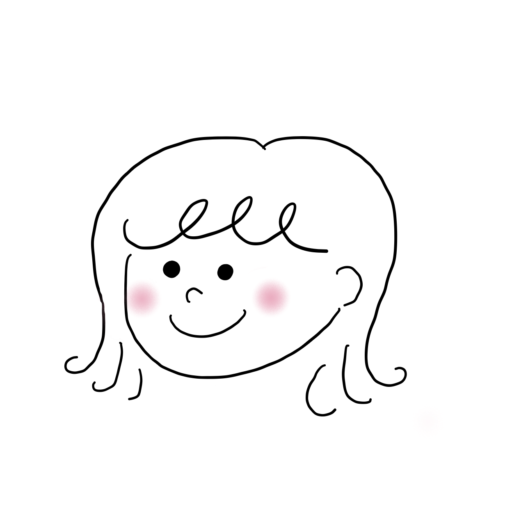
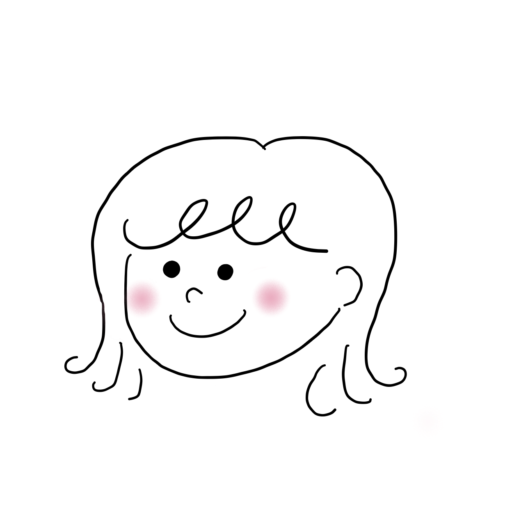
産後間もない精神状態で、公的手続きが多くて混乱しそうになりました。
我が家は、飛行機に乗らなければ移動できない距離にある実家へ里帰り出産であったこと、夫の仕事が多忙であったことなどが重なり、手続きが煩雑になりました。
効率よくできるだけ早く手続きをする順番は、以下のとおりでした!
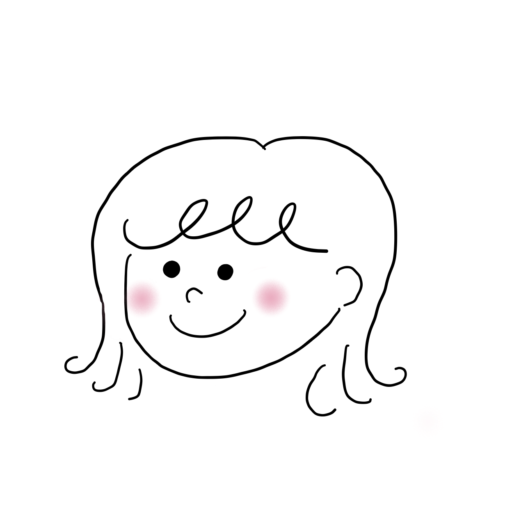
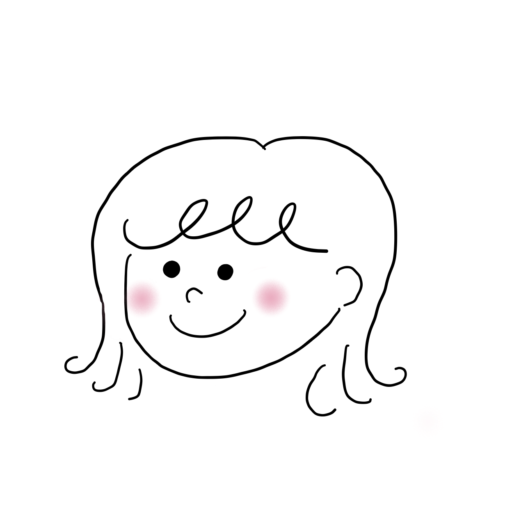
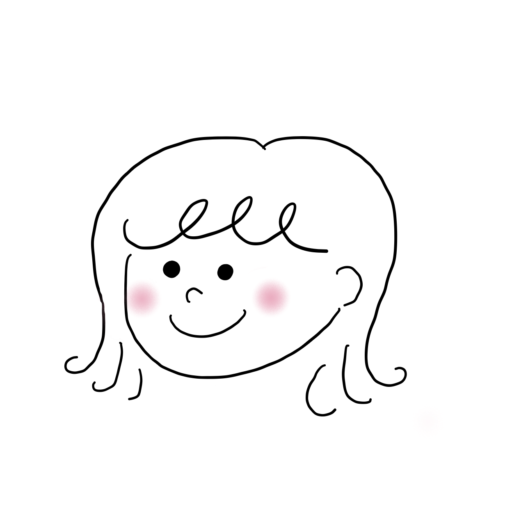
一つ一つ、パートナーと一緒にやっていきましょう。
①最短を求めるなら、出生届は居住する自治体に提出する
産後、様々な手続きをするにしても、まずは出生届を提出しなければ始まりません。
出生届は、出産した地域の自治体に提出することもできますが、その自治体で受理・手続きをし、住民票のある自治体へ転送されるまでに時間がかかります。(最短でも1週間程度は見ておく)
さらに、住民票のある自治体に転送されてからも、手続き後住民票にあかちゃんの情報が反映されるまでに、数日かかることがあります。(大体1~2日程度)
最短で住民票を入手したい場合は、直接住民票のある自治体に出生届を出しましょう。
②住民票を取得し、健康保険証の申請
出生届を提出し、住民票が取得できたら、健康保険証の申請をします。
勤務先の健康保険組合または、自治体の国民健康保険窓口に申請しましょう。
③健康保険証の申請と合わせて、高額医療費制度の申請
あかちゃんの医療費が高額になりそうな場合は、健康保険証の申請と同時に、高額医療費制度の「限度額適用認定証」を申請しておくとスムーズです!
④健康保険証ができたら、「子ども医療費助成」の申請
健康保険証ができたら、速やかに「子ども医療費助成」の申請をしましょう。
健康保険証の発行が、退院時や医療費の支払い時に間に合わない場合は?
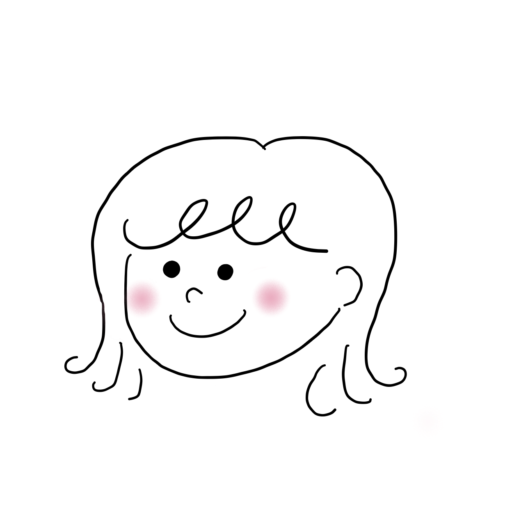
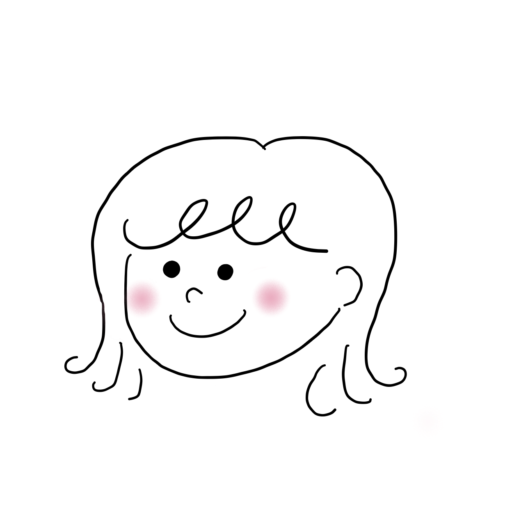
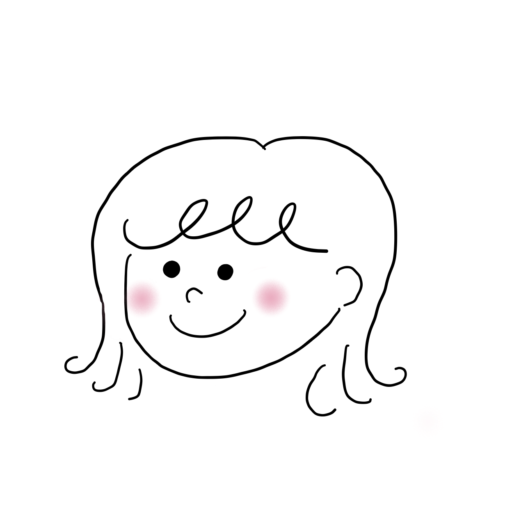
生まれてすぐ治療する場合、保険証が間に合わないことはよくあることみたいです!!
健康保険証や限度額認定証の入手が、医療費の支払い時に間に合わない場合、窓口で一時的に全額自己負担しなければいけません。
しかし、医療費が高額すぎて、一時的であっても全額自己負担で支払うのが難しい場合があります。
支払い金額が高額で支払いが困難な場合は、病院によっては、健康保険証や限度額適用認定証が出来上がった後に、支払えばよいとしてくれる場合もあります。
息子の入院した病院では、事前に相談したところ、退院日に保険証が間に合わなかった場合は、一時金(保険適用外の費用のみ)を退院時に支払い、残りは健康保険証ができあがってから支払うかたちになると言われました。
結局、我が家は息子の退院時に保険証のみ間に合いましたが、病院側の融通が利くことに安心しました!
病院によって対応が異なりますので、早めに相談しておきましょう。
産後は心身が不安定…各担当窓口を頼りましょう!


産後間もない女性は身体も心も不安定なもの。
万が一あかちゃんへ医療行為が必要となってしまった場合、心配で心までボロボロになってしまうこともあると思います。
一人で考え込まず、家族や親族と一緒に今後を考えましょう。
そして、利用する制度のことや手続き手順について困難なことがある場合は、すぐに自治体や健康保険組合、医療機関などに問い合わせましょう。
些細なことでも大丈夫!
関係機関を頼って、効率よく必要な手続きを進めましょう。

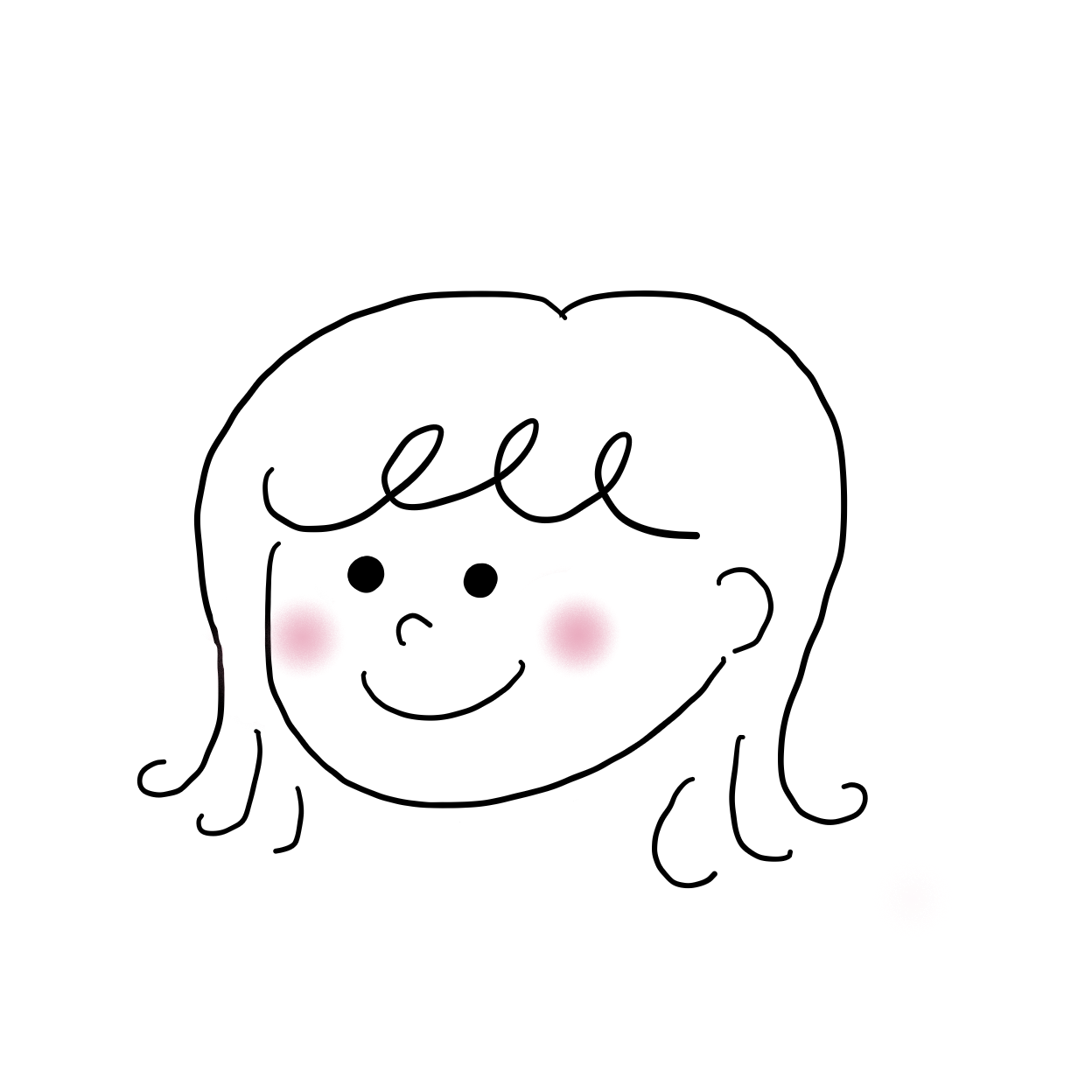
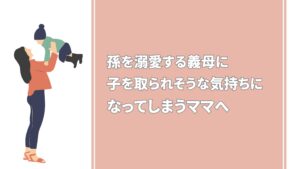
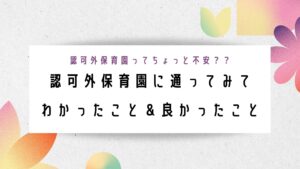
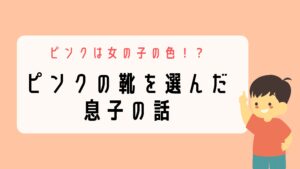
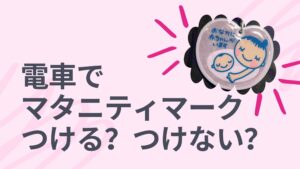

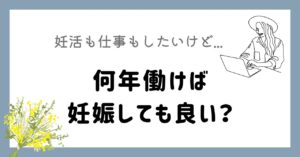

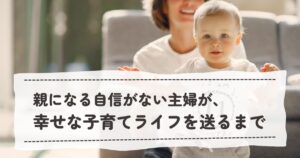
コメント